
日常生活の中で、立ち上がったときにめまいやふらつきを感じたことはありますか?
立ちくらみ症状が頻繁に起こる場合、「起立性低血圧」の可能性があります。
特にパーキンソン病の患者さんでは、自律神経の働きが低下しやすく、血圧の調節がうまくいかなくなるため、症状が顕著に現れます。今回は、理学療法士の視点から、起立性低血圧の評価方法や改善に向けたリハビリプログラムについて詳しく解説していきたいと思います。
そもそも起立性低血圧とは?
起立性低血圧とは、横になっている状態や座っている状態から立ち上がったときに血圧が急激に下がることで、めまいや失神などの症状が現れる状態です。
立ち上がった際、1〜3分以内に収縮期血圧が20mmHg以上、または拡張期血圧が10mmHg以上低下する場合に診断されます。通常であれば、立ち上がると重力の影響で血液が下肢に溜まりますが、自律神経が正常に働いていれば、血管が収縮して血圧を維持します。しかし、パーキンソン病や神経変性疾患の患者さんでは、この調節機能が低下してしまうため、脳に十分な血流が届かなくなり、ふらつきや失神につながるのです。
起立性低血圧が起きるメカニズム
起立性低血圧が起きるメカニズムについてもう一歩踏み込んで詳しく解説しますね。起立性低血圧では、立ち上がったときに 心臓や自律神経の反射が遅れる ことで、血圧の調整がうまくいかなくなります。
どんな反射が遅れるのかというと、特に関係しているのが バロレセプター反射(圧受容体反射) という仕組みです。これは、血圧が下がったときにすぐに調整するための反射なのですが、起立性低血圧ではこの反応が遅れたり、うまく働かなかったりするんですね。
①バロレセプター(圧受容体)の遅れ
バロレセプターというのは、首の 頸動脈洞(けいどうみゃくどう) や心臓の 大動脈弓(だいどうみゃくきゅう) にある、血圧の変化を感知するセンサーのようなものです。立ち上がったときに血圧が下がると、このセンサーが反応して、
• 心拍数を増やす(頻脈)
• 交感神経を活性化させて血管を収縮させる(血圧を上げる)
という調整をするのですが、起立性低血圧ではこの反応が 遅れたり、弱くなったり します。その結果、血圧が下がり続けて、めまいやふらつきが起こるんですね。
②心拍出量の調整遅れ
通常なら、立ち上がったときに血液が下半身にたまらないように 心拍数を上げたり、心臓の収縮力を強めたり して血圧を維持するのですが、起立性低血圧があると、
• 心拍数を上げる反応が遅れる
• 心臓の収縮力が弱い
• 交感神経の働きが鈍い
といった問題があるため、血液をうまく送り出せなくなり、脳への血流が足りなくなってしまいます。
③血管の収縮反応の遅れ
交感神経がしっかり働いていれば、血管がキュッと収縮して血圧を維持できるのですが、起立性低血圧の人は、
• 交感神経の反応が遅れる
• 血管の収縮がうまくいかない(特に静脈)
といったことが起こるため、下半身に血液がたまったままになり、脳への血流が減ってしまうんです。
これらの反応がうまく機能しないことで、立ち上がったときに「めまい」「ふらつき」「失神」などの症状が起こります。
起立性低血圧の評価方法
起立性低血圧の評価には、まずバイタルサインのチェックが不可欠です。仰臥位で血圧を測定した後、座位、立位へと姿勢を変えながら1分後と3分後に再測定します。血圧の変動を確認することで、どの程度の低下があるのかを判断します。加えて、心拍数の変化も重要な指標となります。通常、立ち上がると心拍数が10〜20拍程度増加しますが、パーキンソン病の方では自律神経機能が低下しているため、この心拍の上昇が乏しくなり、血圧が十分に調整できなくなってしまいます。こういった起立試験を行うことで、血圧の連続変動を詳しく調べることができます。
また、ふくらはぎの筋力や歩行能力を確認することも重要で、特に下肢の静脈還流を促す筋力が低下していると、血圧の急低下を引き起こしやすくなります。さらに、生活習慣として、水分摂取量や食事の内容、運動習慣なども評価することで、症状の悪化要因を多面的に考えていく必要があります。
起立性低血圧を改善するリハビリ方法
起立性低血圧の改善には、理学療法によるリハビリが有効です。特に、下肢の筋力を強化することで血液の循環を促し、立ち上がった際の血圧低下を抑えることができます。
①足腰の筋力を強化する(特にふくらはぎ)
ふくらはぎの筋肉である腓腹筋やヒラメ筋は、血液を心臓へ戻すポンプの役割を果たしており、これらを鍛えることで血流が改善されます。例えば、つま先立ちを繰り返し行うことで、ふくらはぎの筋力を向上させることができます。また、足首をゆっくりと上下に動かしたり、椅子に座った状態で膝を伸ばす運動を取り入れることで、下肢の血流を促進する効果が期待できます。
②有酸素運動で心肺機能を強化する
有酸素運動を行うことで心肺機能を向上させ、自律神経の働きを整えることができます。ウォーキングを1日10分ずつ3回に分けて行うだけでも、血圧の調整機能が向上します。負荷の少ない自転車エルゴメーターや、水の浮力を活かしたプールでの歩行運動も効果的です。自分の体力に合わせて、無理のない範囲で続けることが重要です。
③生活習慣を見直す
水分・塩分の摂取
十分な水分を摂取し、1日1.5〜2リットルの水分をこまめに補給することで、血圧の急激な低下を防ぐことができます。また、適度な塩分を摂ることも血圧の維持に役立ちます。ナトリウムの摂取量を2〜3g程度に調整し、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。食後に急に立ち上がると血圧が下がりやすいため、食後はしばらく座って休むようにしましょう。
圧迫ストッキングの活用
圧迫ストッキングを活用することで、下肢の静脈還流をサポートし、血圧の低下を抑えることができます。特に、20〜30mmHg程度の圧力がかかるストッキングを選ぶと効果的です。寒い環境では血管が拡張しやすく、血圧が低下しやすいため、冷え対策をしっかり行うことも重要です。
起立時の工夫
起立性低血圧の方は、日常生活の中で立ち上がる際の工夫をすることで、症状を軽減することができます。急に立ち上がるのではなく、まず座位でゆっくりと落ち着いた後に立ち上がるようにすると、血圧の急激な低下を防ぐことができます。長時間の立位は避け、30分ごとに足を動かして血流を促すことも有効です。さらに、低血圧の兆候を感じたらすぐに座り、無理をしないことが大切です。
まとめ
起立性低血圧は、単なる「立ちくらみ」ではなく、生活の質を大きく左右する症状です。
しかし、適切なリハビリと生活習慣の改善を行うことで、症状を和らげることが可能です。
特にパーキンソン病の患者さんにとっては、こうしたリハビリが日常生活の安定につながるため、一人ひとりの状態に合わせたプログラムを提供することが重要です。お悩みの方は気軽のご相談ください。



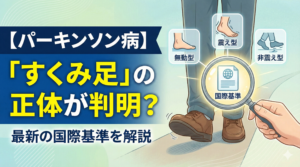

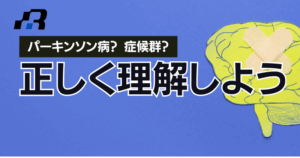





コメント