
今回は、パーキンソン病の患者さんがよく悩まれる「すくみ足(FOG:Freezing of Gait)」に関する、世界的に注目された2022年の研究をご紹介しながら、どんなリハビリが効果的か、一緒に考えてみましょう。
 白石
白石「歩きたいのに、足が出ない…」という悩み、実は多くの患者さんが感じていて、リハビリ現場でも最も相談が多い症状のひとつです。
そもそも「すくみ足」ってなに?
パーキンソン病の進行とともに、歩こうとしたときに足が地面に張り付いたように動かなくなることがあります。これが「すくみ足(FOG:Freezing of Gait)」です。
• ドアの前
• 人混みの中
• 曲がり角
• 歩き出しや方向転換のとき
こういった場面でよく起こり、転倒のリスクが高くなってしまいます。



すくみ足は転倒のきっかけにもなるので、放っておかず、対策していくことが大切です!
今回紹介する研究について
この研究は、香港大学やオランダの神経内科医らの国際チームによってまとめられたもので、「どのリハビリがすくみ足に効果的なのか?」を明らかにするため、53の研究・2,300人以上のデータを比較しました。
このような「ネットワーク・メタアナリシス」と呼ばれる手法は、複数の治療法を同時に比較できる強力な方法です。
どんなリハビリが調査されたの?
調査対象となったのは以下のようなものです。
• トレッドミル歩行(ルームランナーでの歩行訓練)
• ノルディックウォーク(ポールを使った歩行)
• 水中トレーニング
• 認知運動療法(動作のイメージトレーニングなど)
• ダンス
• 外部キューイング(音や光の合図によって動作を促す訓練)
• 一般的な理学療法(バランス・筋力訓練など)



最近では、自費リハビリの領域でもノルディックウォークやダンス、VRを使ったリハビリが注目されています。
結果①:全体として「中等度の効果あり」
まず研究全体として、「どの方法であれ、リハビリを行ったグループは、なにもしないグループに比べて、すくみ足の症状が軽くなった」ということがわかりました。
具体的には、効果量(エフェクトサイズ)は -0.37 と報告されていて、これは「中程度の改善があった」と解釈されています。
※効果量(エフェクトサイズ)とは、治療や介入によってどれだけの効果があったかを示す指標です。
一般的には、0.2が「小さい効果」、0.5が「中くらいの効果」、0.8以上で「大きな効果」とされています。
今回の -0.37 はマイナスの数値ですが、これは「症状のスコアが減った(=改善した)」ことを意味していて、大きさとしては“中等度の改善”と判断することができます。
※マイナスだから悪いというわけではありませんのでご安心ください。



つまり「やらないより、やった方がずっといい!」ということ。これはとても心強い結果です。
結果②:特に効果があった運動は?
この研究の面白いところは、「どれが一番効果的か?」を比較してくれている点です。特に効果が高かったとされたのは……
• トレッドミル歩行
• ノルディックウォーク
• 高難易度のレジスタンストレーニング
これらは、すくみ足だけでなく、歩行速度や歩幅にもいい影響がありました。
高難易度のレジスタンストレーニングとは、ただの筋トレではなく、「体幹の安定を保ちつつ脚を動かす」といった、動作の中にバランスやコーディネーション要素が組み込まれたトレーニングです。
例:立位での片脚スクワット+上肢の交互運動、ゴムバンドを使ったクロス運動など
「高難度=キツイ」ではなく、「高難度=全身を協調させながら、考えて動くような動作」というニュアンスです。
こうした運動は、すくみ足の原因とされる運動と認知の連携の障害(前頭葉と基底核のネットワークの問題)にアプローチできる可能性があるため、有効ではないかと考えられています。
もし、リハビリプログラムや自費リハビリで「高難度の運動」が取り入れられているかを見たい場合は、「複数部位の協調性を必要とする動作があるか?」が一つの判断ポイントになりますよ。



「高難度の運動」=体と頭の両方を同時に使う動きがカギのようです!
結果③:意外と効果がはっきりしなかったもの
一方で、以下のようなリハビリでは、明確な改善効果が確認されなかったという結果になりました。
• 外部キューイング(音・光の合図)
• デュアルタスク(歩きながら計算など)
• 太極拳やヨガなどの運動
• ダンス療法(これは意外ですね)
これは、「歩行そのもの」よりも、「注意力や反応速度」などがすくみ足に関係しているためでは?と研究では考察されています。



外部キューだけだと、脳が「受け身」の状態になってしまって、根本的な改善にはつながらないのかもしれませんね。
リハビリの頻度・時間・期間はどれくらい?
では、すくみ足に効果があったリハビリは、どのくらいの量・頻度でやっていたのでしょうか?
• トレッドミル:20〜45分/回、週2〜7回、4〜6週間
• ノルディックウォーキング:60分/回、週2回、12週間
• 一般的な理学療法:40〜90分/回、週2〜3回、4週間〜6ヶ月



無理せず、自分のペースで「継続できる」ことが何より大事ですね!
自費リハビリを選ぶときのポイント
この研究から得られるヒントをもとに、自費リハビリを選ぶときには、次のような点をチェックしてみてください。
• 「すくみ足」に特化したプログラムがあるか
• ノルディックウォーク(姿勢を正した状態での歩行)や高難易度の筋トレを取り入れているか
• 定期的に専門家によるフィードバックがもらえるか
• 実施頻度・期間が自分の体力や生活に合っているか



私の現場でも、自費リハビリでしっかり改善している方、多いです。無理なく「続けられる環境」が成功のカギですよ!
最後に:すくみ足は「あきらめない」が大事
「すくみ足」は、なかなかコントロールが難しい症状ですが、リハビリで改善の可能性があることが、この研究でもはっきりしています。
特に、単なる「筋トレ」や「バランス訓練」ではなく、体と脳を同時に使うような複雑な運動が、症状改善のカギになるということが、今回の大きな発見です。
そしてもう一つ大切なのは、「自分に合った方法で、継続していくこと」です。
焦らず、少しずつでも進んでいきましょう。



「また歩けるようになった!」という患者さんの笑顔を見ると、私たちも勇気をもらえます。一緒に、できることから始めましょう!
参考文献(原著論文)
Kwok, J.Y.Y. et al. (2022). Managing freezing of gait in Parkinson’s disease: a systematic review and network meta-analysis. Journal of Neurology, 269(7), 3325–3327.
URL: https://doi.org/10.1007/s00415-022-11031-z



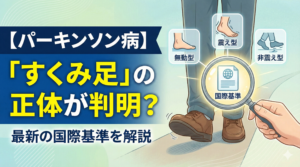

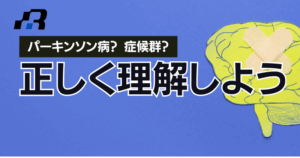





コメント