質問内容
「昨年パーキンソン病と診断を受けたばかりで、主治医の先生からはリハビリを勧められた方から「どの程度やったらいいのでしょうか?」
結論としては、
「出来るだけ診断された早い時期から、色々な種類の集中的なリハビリプログラムを積極的にやった方が良い」
と私は考えています。
今回は、その理由について解説しますね。
パーキンソン病患者さんは、診断を受けたあと主治医から薬物療法に併用してリハビリを勧められます。
ただ、具体的なリハビリ内容にまで言及されることは少ないため、”どんな運動を、どのような頻度で”行ったら良いのか悩んでいるパーキンソン病者さんも良く出会います。
そこで今回はリハビリの具体的な方法について言及された文献をベースを紹介したいと思います。
Frazzitta G, Maestri R, Bertotti G, Riboldazzi G, Boveri N, Perini M, Uccellini D, Turla M, Comi C, Pezzoli G, Ghilardi MF. Intensive rehabilitation treatment in early Parkinson’s disease: a randomized pilot study with a 2-year follow-up. Neurorehabil Neural Repair. 2015 Feb;29(2):123-31. doi: 10.1177/1545968314542981. Epub 2014 Jul 18. PMID: 25038064.
この論文では、イタリアの発症早期のパーキンソン病患者31名を対象に、薬物治療と併用して集学的集中リハビリテーション治療(MIRT)を行ったグループ16名と薬物治療のみを行ったグループ15名で比較して2年間追跡したところ、集学的集中リハビリテーション治療を行ったグループでは薬の追加が少なくて済んだそうです。
そもそも、”集学的集中リハビリテーショングループ”という言葉自体、聞き慣れないのでご存じの方も少ないのではないでしょうか?
まず”集学的”という言葉馴染みが薄いですが、医療の世界で使われている用語で、専門分野が異なる複数の医師や専門スタッフがチームとなって行う治療に対して使われます。
診療科を超えて各分野の専門職が協力して治療を行う「集学的」という考え方は、神経内科の領域では近年特に重要視されています。
集学的集中リハビリテーションは、英語ではMultidisciplinary Intensive Rehabilitation Treatmentであり、”MIRT”と呼ばれています。
《用語のまとめ》
Multidisciplinary:集学的
Intensive:集中
Rehabilitation:リハビリテーション
Treatment:治療
実際、MIRTではどんなことをしていたかというと、
1日3時間のプログラムを週5日✖️4週間、合計20回行うというものでした。
これだけで、かなりハードなプログラムである事は容易に想像できますね。
「3時間も運動なんて無理」と感じた方も居るのではないでしょうか?
もう少しプログラムの具体的な内容を深ぼってみると、3時間の内訳としては以下の通り。
《1日3時間のリハビリプログラム内訳》※1回60分を3回に分けて実施しています
- ウォーミングアップ
- リラクゼーション
- ストレッチ
- 可動域改善エクササイズ
- バランス&歩行改善エクササイズ
- スタビロメトリック・プラットフォームを利用した視覚バランストレーニング
- トレッドミルを使用した有酸素運動30分(速度は3.5km/hなので速くも遅くもない普通歩行)
- 立ち上がり運動
- 寝返り・起き上がり運動
- 着替え訓練
- 手指の巧緻訓練
正直、これだけのプログラムをほぼ毎日1ヶ月間もやっていれば誰でも効果出そうな気がしますよね。私自身がこのプログラムをやっても変化が出そうです。
この研究ではラサギリン(アジレクト)と言われるMAO-B阻害薬のお薬を使用していたのですが、MIRTを実施したグループでは薬の増量は少なく、追加もしないで済んでいる割合が多かったという結果でした。
MAO-B(monoamine oxidase -B:モノアミン酸化酵素のBタイプ)は、ドパミンを脳内で分解してしまいやすく、MAO-B阻害薬によってこの分解してしまう働きをを抑えることで、結果的にドパミンが働きやすくなってパーキンソン病の症状を改善するというものです。
現在、日本では3種類セレギリン(エフピー)、ラサギリン(アジレクト)、サフィナミド(エクフィナ)が使用可能です。
今回の記事では、”出来るだけ診断された早い時期から、色々な種類の集中的なリハビリプログラムを積極的にやった方が良い”理由について解説しました。
とは言っても、集中的な運動を1人で実施することは中々困難な方も多いかと思いますので、まずはパーキンソン病のリハビリに詳しい専門家へご相談することをお勧めします。




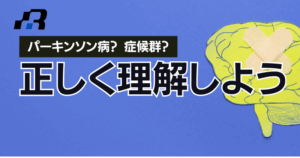





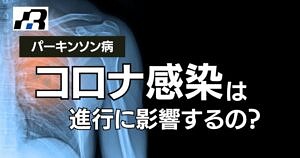
コメント