
今回は、パーキンソン病の方から我々理学療法士に対して必ず質問で出てくる「運動って脳に良いってホント?」という疑問に対して解説したいと思います。
テーマは「運動で脳の機能を改善できるのか?」という、まさにリハビリの本質に迫る内容です。
紹介する論文は、ポーランドの研究グループが2014年に発表した論文で、パーキンソン病患者さんが週3回、8週間にわたって行った“中等度のインターバルトレーニング”が、脳にとって大切な「BDNF」を増やし、炎症を抑えて、症状の改善にもつながったという報告です。
この論文、パーキンソン病の研修や学会に参加するとほぼ100%紹介されるといってもいいくらい必ず紹介される論文です。
この研究結果は、薬だけに頼らず「運動すること」そのものが、脳の機能を保つための治療になる可能性を示してくれています。
「薬だけでなく運動もしましょう」と繰り返し言っているのはこの論文からも伝わるのではないかと思います。
そもそもBDNFってなに?
まず、「BDNF」という言葉をご存知ない方がほとんどかと思います。
BDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor)とは、「脳由来神経栄養因子」といい、脳の中で働く「栄養因子」で、神経細胞の成長や維持・再生などをサポートしてくれるめちゃくちゃ大事な因子です。
いわば、脳の“肥料”のようなもので、脳内ネットワークの柔軟性や記憶、学習、気分の安定など様々な働きを担ってくれています。
最近の研究では、パーキンソン病の方は健常な方と比べて「BDNFの血中濃度が低い」ことがわかってきており、この因子を増やす方法が注目されています。
 白石
白石BDNFは、いわば、脳の“肥料”のようなもので、脳内ネットワークの柔軟性や記憶、学習、気分の安定など様々な働きを担ってくれています。
最近の研究では、「パーキンソン病の方は健常な方と比べてBDNFの血中濃度が低い」ことがわかってきており、この因子を増やす方法が注目されています。
研究の詳細内容
この研究を行ったのはポーランドの研究者で、研究対象者は12名のパーキンソン病患者さん。
平均年齢70歳でパーキンソン病の診断を受けてからおよそ8年経過した12人の方々(男性7名、女性5名)。
週3回・1時間の自転車エルゴメーターを使った中等度のインターバルトレーニングを8週間実施して、その前後で血液中のBDNFや炎症マーカー、そして症状の変化を見ていきました。
以下のような自転車エルゴメーターを使った中等度のインターバルトレーニングです
・週3回、1時間ずつのトレーニング(合計24回)
・ウォームアップ10分(ゆっくり自転車こぎ)
・3分間のやや速いペース(80–90回転/分)と、2分間のゆっくりペース(60回転/分未満)を交互に繰り返す(合計40分間)
・クールダウン10分
上記のように、高い負荷と低い負荷を交互に行う「インターバル形式」の運動を行いました。
※注意点としては、薬が効いている「オン」の時間帯に実施しています



運動強度にメリハリをつけた“インターバル”がポイントです。
同じペースよりも神経への刺激が入りやすいんですよ。
この運動強度は「中等度」とされています。つまり、ハードすぎず、でも決して軽すぎないちょうど良い強度になります。
目標最大心拍数の60~75%の範囲で心拍数をコントロールしながら、安全な環境下で行われました。
その結果、どんな変化があったのでしょうか。
結果その1. BDNFが34%アップ!
運動前のBDNF:10,977 pg/mL → 運動後:14,206 pg/mL
BDNFの血中濃度の正常範囲は、研究によって多少異なりますが、一般的な健常成人のBDNF濃度(血清中)は
約7,000〜20,000 pg/mL と言われています。
つまり、運動前:10,977 pg/mL → 運動後:14,206 pg/mL というのは、
「正常範囲内ではあるが、しっかりと上昇している」ことがわかります。
結果その2. 症状が明らかに改善(UPDRSスコア)
UPDRSという症状の重さを示す指標で、平均して48.9点から38.1点に改善しました。
つまり、日常の動作が楽になった可能性があります。
結果その3. 炎症マーカーが大きく減少
• sVCAM-1(血管の炎症マーカー):約21%減少
• TNF-α(炎症性サイトカイン):約7%減少
さらに、なんと言っても重要なポイントが「副作用がなかった」という点です。
・血中のストレスホルモン(コルチゾール)
・酸化ストレスの指標(F2-イソプロスタン)には変化がなく
運動そのものが体への悪影響はなかったことがわかりました。
運動するとBDNFが増えるメカニズム
BDNFは脳で作られて血液中に放出されるんですが、運動することによって脳や血管の細胞が刺激され、BDNFの分泌が促進されると考えられています。
さらに、炎症も収まることで脳機能が改善し、それがBDNFの増加を促進しした可能性もあります。
ではどのくらいの運動強度がいいかというと、「運動の強度」です。
今回の研究はエアロバイクを使った研究ですが、必ずしもエアロバイクである必要はありません。
重要なのは、「そこそこしっかり」汗をかく程度の強度「中程度」です。
この運動強度に関しては、プロエルの中でも繰り返しお伝えしているのでご存知かと思います。
プロエルの運動プログラム、リハトレスタジオ世田谷で実施しているオンラインフィットも「中程度」の運動強度を目指したプログラム設計しています。



リハトレスタジオ世田谷のオンライン運動レッスンはこれらの研究をもとにプログラム設計しています。
また、今回の研究は「インターバル形式」で行われた点に関して、単調な運動よりも、リズムや強弱をつけることで、より神経への刺激が入りやすくなる可能性があるという点は、日常でもうまく取り入れるといいかと思います。
ウォーキングをする際も、一定のペースで淡々と歩くのではなく、「5分ゆっくり1分速く」という感じで強度を強弱することで脳にも刺激が入りやすくなるかもしれないので、日々のウォーキングでもお試しください。
まとめ
今回の研究から得られるメッセージは、以下のような点に集約されます。
• 中等度のインターバルトレーニングは安全かつ効果的
• たった8週間の運動でも、BDNFが増えて、炎症が抑えられ、症状が改善
• リハビリは“筋肉”だけでなく、“脳”にも影響を与えうる



リハビリは、動きの改善だけありません。
“神経の回路を再構築する”ということも運動の目的になります。
パーキンソン病における理学療法とリハビリの可能性は、今後さらに広がってきています。
運動を“脳を育てる手段”としてとらえる視点、ぜひ多くの方に伝えていきたいと思います。
参考文献
Zoladz JA, Majerczak J, Zeligowska E, et al. (2014). Moderate-intensity interval training increases serum brain-derived neurotrophic factor level and decreases inflammation in Parkinson’s disease patients. Journal of Physiology and Pharmacology, 65(3), 441-448.
https://www.researchgate.net/publication/263131632



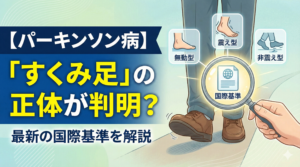

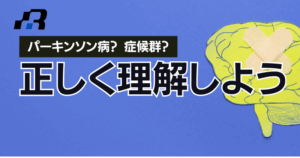




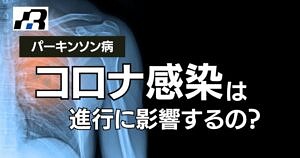
コメント