このたび、代表の白石が認定理学療法士(神経筋障害・介護予防)に合格しました。
本記事では、この資格の概要や、各分野について詳しく解説し、今後の活動についてお伝えします。
認定理学療法士とは?
認定理学療法士とは、日本理学療法士協会(JPTA)が認定する資格で、特定の専門分野において高度な知識と技術を有する理学療法士に与えられます。
この資格は、研修や学術活動を経て、試験に合格することで取得できます。
あまり「認定」理学療法士という言葉に聞き馴染みはない方も多いかと思いますが、医師の領域で例えるとイメージがつきやすいのではないでしょうか。
医師の領域には整形外科・内科・神経内科・循環器科など多くの診療科があるのはご存知かと思います。
理学療法の領域も医療の発展とともに細分化していっており、現在は以下の21領域に分かれています。
- 脳卒中
- 神経筋障害
- 脊髄障害
- 発達障害
- 運動器
- 切断
- スポーツ理学療法
- 徒手理学療法
- 循環
- 呼吸
- 代謝
- 地域理学療法
- 健康増進・参加
- 介護予防
- 補装具
- 物理療法
- 褥瘡・創傷ケア
- 疼痛管理
- 臨床教育
- 管理・運営
- 学校教育
現在では上記の領域に分科しているのですが、今回私が受験したのは「神経筋障害」と「介護予防」になります。
認定理学療法士を取得するためには約5年ほど以下に挙げる研修プログラムを受講する必要があります。
理学療法士として働き始めたら、まずは「新人教育」を受けることになります。これは、「基礎訓練」のようなもので、社会人として、そして医療従事者としての注意を学ぶ時期です。例えば、スポーツチームに入ったばかりの選手が、チームのルールや練習方法を覚えたり、基本的な体づくりをするのと同じです。
ここでは、医療現場でのマナーや患者さんの接し方、理学療法士としての倫理観、そしてチーム医療の中での役割などを学びます。理学療法の知識や技術ももちろん大切ですが、その前に「プロとしての姿勢」をしっかり身につけることが求められます。
新人教育が終わったら、次に進むのが「前期」です。これは、理学療法士としての基礎をしっかり固める期間で、「基礎コース」のようなものです。
前期研修では、一次救命措置やリスク管理、症例報告の方法など、現場で使える基本スキルを学びます。また、実際の研修も含まれていて、実際の患者さんに対してどのように評価をし、どのようなアプローチをするかを考えていきます。
これは、より実践内容に踏み込んで時期的に、「応用コース」と言えます。スポーツで例えるなら、練習試合を繰り返して実践経験を積むようなものです。
後期研修では、より専門的な知識や技術を学びながら、様々な患者さんに対応する力をつけていきます。例えば、「この患者さんの歩行障害にはどんな治療法が適しているのか?」のような、臨床推論トレーニングも含まれます。
これは、自分の専門分野を選択して学ぶ段階で、大学らしい「専門演習」のようなものです。
これは、一般的な理学療法士から一歩進んで、特定の分野で活躍できるプロフェッショナルになるための研修です。 例えば、サッカー選手が「フォワードの専門スキルを確実に磨く」ようなものです。
最後のステップが「21領域に分かれた専門研修プログラム」です。これは、さらに高度な知識や技術を身につけるための研修で、「プロフェッショナル養成コース」を決めます。例えば、トップアスリートがオリンピックに向けて、特別なトレーニングを受けるようなものです。
この研修では、各領域に関する最新の研究やエビデンスを学びながら、理学療法の最前線で活躍できる力をつけていきます。また、自分自身が指導者としての権利を育てたり、学会発表や論文執筆など優しく、理学療法の発展に貢献する役割も求められます。
神経筋障害領域とは?
神経筋障害領域は、主に神経難病に対するリハビリテーションを専門とする分野です。
対象となる主な疾患
- パーキンソン病
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- ギラン・バレー症候群
- 多発性硬化症
- 筋ジストロフィー
- 末梢神経障害(CIDPなど)
神経難病のリハビリでは、病気の進行を遅らせ、生活の質(QOL)を向上させることが大切です。
私は、これまでパーキンソン病のリハビリテーションに力を入れてきましたが、今回の認定を通じて、より専門的な視点でのアプローチが可能になりました。
介護予防領域とは?
介護予防領域は、高齢者の要介護状態を防ぎ、健康寿命を延ばすことを目的とする分野です。
介護予防領域の主な対象
- フレイル(加齢による体力低下)
- サルコペニア(筋力低下)
- 転倒・骨折の予防
- 認知症予防
- 運動器不安定症の改善
認定理学療法士の取得者数
認定理学療法士は、特定の分野で高度な知識と技術を持つ理学療法士として、日本理学療法士協会によって認定される資格です。2024年3月31日時点で、約21万人いるのですが、認定理学療法士の取得者数は延べ17,145名となっています。
分野別の取得者数を見ると、以下のようになっています。
分野別の認定理学療法士取得者数
- 運動器: 4,665名
- 脳卒中: 3,898名
- 地域理学療法: 1,478名
- 呼吸: 1,484名
- 介護予防: 583名
- 神経筋障害: 234名
介護予防と神経筋障害領域はいずれも人数は少ないですね。
2024年度の新規合格者数の内訳は以下のとおりです。
今年度の認定理学療法士合格者数
- 神経筋障害: 20名
- 介護予防: 49名
これらのデータから、神経筋障害分野の認定理学療法士は全体の約1.4%、介護予防分野は約3.9%を占めていることがわかります。これらの分野は、他の分野と比べて取得者数が少ないため、専門性を高めることで希少性の高いスキルを持つ理学療法士として活躍できる可能性があります。
まとめ
今回、私は 「神経筋障害」 と 「介護予防」 という2科目を同時受験したのですが、2科目とも、現在取り組んでいる仕事に直結する専門領域だったので学び自体はとても楽しく、充実したものになりました。
認定取得を目指してから5年ほどかかりましたが、なんとか合格できて一安心です。
専門カリキュラム(神経筋障害・介護予防)でお世話になった、国立精神・神経医療研究センター病院、大阪府枚方市理学療法士協会の皆様、本当にありがとうございました!
これからも学び続け、より多くの方に専門的な価値提供をできるよう頑張りたいと思います。


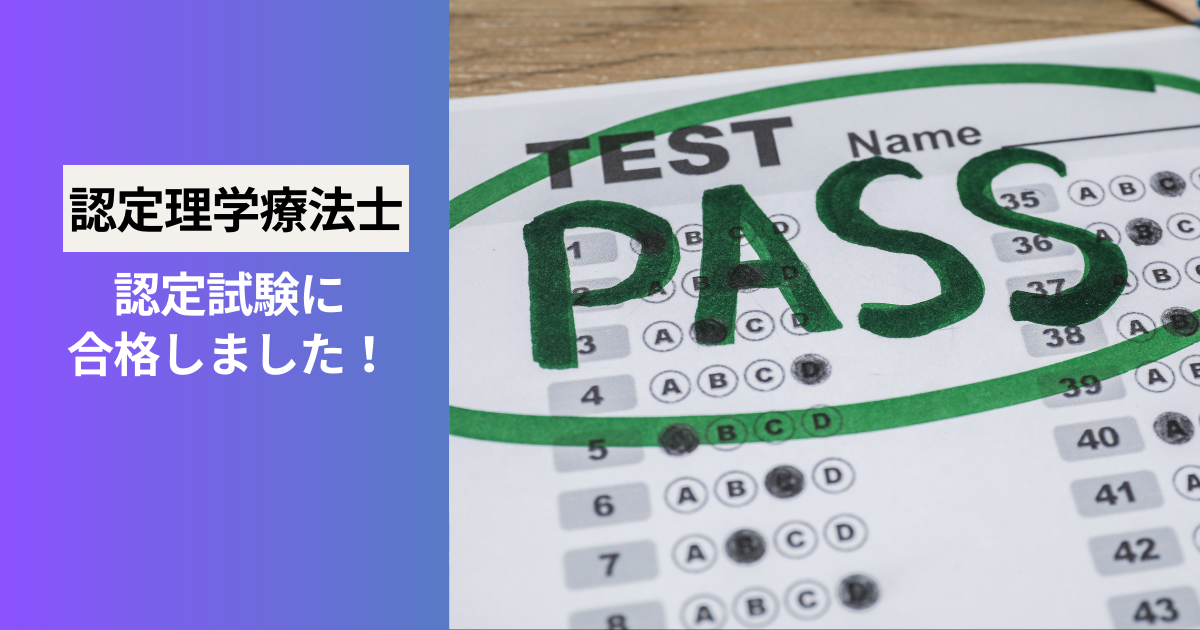



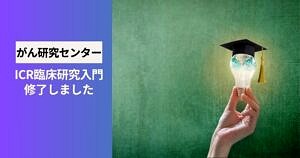

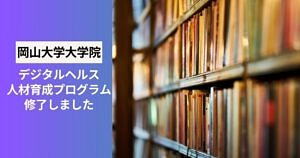


コメント