
今回は、パーキンソン病の患者さんにとってとても重要な「体重の変化」や「代謝の特徴」について取り上げます。特に、「食べているのに痩せる」「筋肉は落ちていないのに体が細くなっていく」という現象に注目した研究をご紹介します。
この研究は、メキシコとスペインの研究チームによって行われたもので、国際的にも信頼性の高い学術誌に掲載されていますA。
この記事では、医学的な専門用語をかみくだいて、日常生活やリハビリにどう役立てられるのかを分かりやすく解説していきます。
体重が減るだけでは分からない!パーキンソン病と体組成の変化
パーキンソン病の方にとって、体重の変化は大きな課題のひとつです。「痩せてきた」と感じるとき、私たちはつい「筋肉が減ってしまったのでは?」と考えがちですが、実際には必ずしもそうではありません。
この研究では、体組成を細かく分析することで、「脂肪と筋肉がどう変化しているのか」を確認しました。その結果、パーキンソン病患者さんは体脂肪が減少している一方で、筋肉量は健常者と大きな差がないことが分かりました。
 白石
白石体重計だけでは分からない“痩せ方の中身”が見えてくるのが、体組成分析の面白いところなんです。
PIGD型パーキンソン病に特徴的な代謝の高さ
パーキンソン病には症状のタイプ分けがあります。
代表的なのは「振戦優位型(手の震えが中心)」と「姿勢保持・歩行困難型(PIGD型)」があるのですが、今回の研究で特に注目されたのは、このPIGD型の方たちでした。
PIGD型(Postural Instability/Gait Difficulty型)
パーキンソン病の臨床タイプのひとつで、「姿勢保持の難しさ」と「歩行障害」が目立つ型を指します。具体的には、ふらつきや転倒のしやすさ、小刻み歩行やすくみ足といった症状が中心で、震え(振戦)は目立たないことが多いです。病気の進行に伴って日常生活に大きな影響を与えやすく、リハビリや転倒予防の支援が特に重要になるタイプです。
PIGD型の患者さんでは、以下の特徴が明らかになりました。
- 体脂肪量・体脂肪率が低い
- 筋肉は維持されている
- 安静時代謝量(RMR)が高い
つまり、PIGD型の方は「脂肪だけが選択的に落ちてしまう」可能性があるのです。



リハビリ現場でも、PIGD型の方は“歩くだけで消耗が激しい”と訴えられるケースが多いです。今回の結果はそれを科学的に裏付けてくれる内容です。
なぜパーキンソン病では代謝が上がるのか?
安静にしていてもエネルギーを多く消費してしまう。
これが安静時代謝量の上昇です。PIGD型では、姿勢を保つために筋肉が常に緊張していたり、固縮(筋肉が硬くなる症状)があるため、余計なエネルギーが消費されていると考えられます。
一方、振戦優位型では震えによるエネルギー消費はあるものの、ここまで顕著な代謝の上昇は見られませんでした。つまり、パーキンソン病のタイプによって“体がどのように消耗するか”が違うのです。
パーキンソン病患者さんの栄養管理とリハビリの工夫
研究の結果を踏まえると、パーキンソン病の方にとって大切なのは「筋肉を守るリハビリ」と「十分なエネルギー補給」です。
- 栄養面での工夫
・体脂肪が落ちやすいため、必要なカロリーをしっかり摂ることが重要です。
・特にたんぱく質と良質な脂質を意識しましょう。 - リハビリで筋肉を維持
・研究では筋肉量は維持されていました。つまり、適切な運動を行えば筋肉は守れるということです。
・歩行練習や筋力トレーニングはもちろん、バランス練習も有効です。 - 生活全体での工夫
・休養と活動のバランスを意識しましょう。
・小まめな間食やエネルギー補給飲料も時に役立ちます。



“痩せている=筋肉が減っている”とは限りません。
リハビリを続けながら食事の工夫をすることで、体力を保てるケースはたくさんあります。
食べているのに痩せる…患者さんの声と体組成チェックの重要性
・「食欲はあるのに、どんどん体が細くなってしまう」
・「以前よりも疲れやすく、歩くとヘトヘトになる」
・「運動しても筋肉が落ちるのではと心配だったけど、体組成を測ったら筋肉は維持できていた」
こうした声は臨床現場でもよく聞かれます。体重や見た目の変化に不安を感じたときこそ、体組成のチェックが大切なのです。
研究から学ぶ!パーキンソン病の体重減少と対策
- パーキンソン病の体重減少は単純ではなく、多くの場合「体脂肪の減少」が背景にある。
- 特にPIGD型では代謝が高く、痩せやすい傾向がある。
- 筋肉は維持される可能性が高いため、リハビリの意義は非常に大きい。
- 食事と運動の両面でのサポートが、生活の質を守るカギになる。
まとめ
- パーキンソン病では、理学療法によるリハビリと栄養管理の両輪で体力維持をめざすことが重要です。
- リハビリは筋肉を守り、パーキンソン病特有の代謝の高さに対処するためにも不可欠です。
- 体組成計による評価は、体重の裏に隠れた体の変化を見抜く手助けになります。



食べているのに痩せる”現象は、病気のせいだと諦める必要はありません。理学療法と栄養の工夫でしっかり対策ができます。
参考文献
Giovana Femat-Roldán, María Andrea Gaitán Palau, Inma Castilla-Cortázar, et al.
“Altered Body Composition and Increased Resting Metabolic Rate Associated with the Postural Instability/Gait Difficulty Parkinson’s Disease Subtype.”
Parkinson’s Disease, vol. 2020, Article ID 8060259, 9 pages, 2020.
https://doi.org/10.1155/2020/8060259
リハトレスタジオ世田谷からのお知らせ
リハトレスタジオ世田谷では、InBody(体組成計)を導入しています。
「最近痩せてきたけど筋肉は大丈夫かな?」「栄養やリハビリの効果を見える形で知りたい」という方は、ぜひ一度測定にいらしてください。
体重だけでは分からない“体の中身”を確認することで、安心できるリハビリ計画や栄養の工夫が可能になります。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。




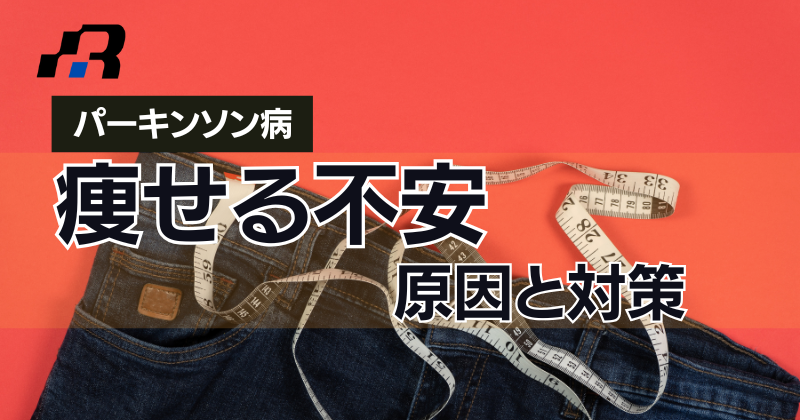
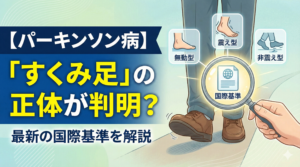

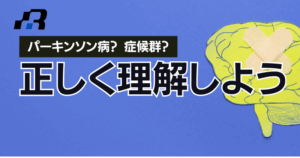




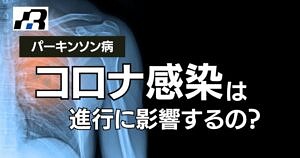
コメント