
今回は、パーキンソン病の方にとって大きな関心事である「運動はなぜ効くのか?」を、2025年に発表された最新の総説論文をもとに解きほぐしていきたいと思います。この論文は、運動がパーキンソン病に与える影響を、多方面から総まとめしたものになります。
私自身、日々のリハビリ現場で「どんな運動をすればいいの?」「本当に効くの?」という質問をたくさんいただきます。そんな疑問に対し、この論文は“なぜ運動が効くのか”を裏づけるメカニズムをわかりやすく示してくれていました。今回はその内容をベースに解説していきますね。
パーキンソン病にとって運動は重要な治療の一つ
パーキンソン病は、脳内でドーパミンを作る神経細胞が少しずつ減ることで、動作の遅れ、震え、こわばり、バランスの崩れなどが出る病気です。
加えて、便秘・睡眠・気分・集中力や記憶の低下などのような「非運動症状」も生活の質に影響します。
今現在の医療ではパーキンソン病の病気そのものを止める治療はありませんが、運動は症状をやわらげ、進行を遅らせる可能性がある“重要な味方”です。
リハビリの場でも、「運動は薬や手術療法と並ぶ大切な治療法の一つ」として扱われています。
 白石
白石運動している方は、同じ罹病期間でも“動ける幅”や“やれる家事の量”に差が出るため、いかに運動を日常生活に取り入れられるかが重要です。
①.神経栄養因子といった脳の“肥料”を増やす
運動には、脳の神経を守る“肥料”のような物質を増やす働きがあります。
神経栄養因子の中でも代表的なのが「BDNF(脳由来神経栄養因子)」や「GDNF(グリア細胞由来神経栄養因子)」です。これらの神経栄養因子は神経細胞の寿命を延ばし、神経同士のつながりを保つ役割を持っています。
BDNFやGDNFという物質は、脳の神経を元気に保つサポート役です。
たとえるなら、植物にとっての肥料や水のような存在です。BDNFは「TrkB(トラックB)」、GDNFは「RET(レット)」という“受け皿”を通して、神経細胞に対し、「もっと元気に働こう」という指令を送ります。
さらに、CDNFやMANFという物質もあります。これは、神経の中にある“小胞体”という作業場で起きるストレスを静める役割を持っています。小胞体は細胞の工場のようなもので、ここが疲れてしまうと神経が弱ってしまいます。CDNFやMANFはその疲れを取って、特にドーパミンを作る神経を守る方向に働いてくれると考えられています。
こういった物質を外から薬のように入れようという研究は昔から行われていますが、うまくいったりいかなかったりで、安定した結果はまだ出ていません。しかし、わざわざ外から薬を入れるのではなく、運動をすることによる“自分の体の中から”これらの物質を増やす方法は、研究でも良い結果がたくさん報告されています。
実際、パーキンソン病の方の血液を調べると、運動のあとにBDNFが増え、その指令を伝えるスイッチ(TrkB)がしっかり働き始めることがわかっています。つまり、特別な薬を使わなくても、運動があなた自身の体の中に“神経を守る物質”を生み出してくれるのです。運動の効果ってすごいですよね。
効果が出やすいのは、強度が低すぎない運動です。たとえば「少し息が上がる」くらい、つまり会話はできるけれど鼻歌を歌うのは難しい程度。この強度で15〜25分、週に3〜4回を目安にするとよいかと思います。
ただし、無理は禁物なので、歩くのが不安な場合は、屋内バイクや水中歩行、ステップ運動など、安心してできる方法から始めてみてください。
また、運動の前後には必ず血圧やふらつき、痛みがないかを確認しましょう。パーキンソン病では、その日の体調によって“できる量”が大きく変わることも珍しくありません。そんな時は、“調子が良い日バージョン”と“しんどい日バージョン”のように2パターンを用意しておくと、続けやすくなります。



“今日は短くてもゼロにしない”がコツです。
運動がゼロだと再開が辛くなるので、2-3分でもいいのでやりましょう。
②.脳の信号バランスを整える
パーキンソン病では、脳の中で「ドーパミン」という動きをスムーズにする物質が減ってしまいます。すると、神経同士のやり取りのバランスが崩れ、「興奮の信号」が強く残ってしまう状態になります。
これは、車でアクセルを踏みっぱなしにしているようなもの。信号が出っぱなしになると、神経の先端が傷みやすくなり、情報を伝える道が細くなったり途切れたりします。その結果、体を動かそうとした時にうまく動き出せなかったり、途中で動きがぎこちなくなったりします。
運動には、この「興奮しすぎた信号」を落ち着ける力があります。さらに、傷んだ神経の先端を少しずつ回復させ、再び情報が通りやすい道を作る働きもあります。
人を対象にした研究では、パーキンソン病の方がランニングマシンでの運動を6カ月続けたところ、脳の中で動きに関わる部分が元気を取り戻し、健康の目安となる数値も改善したという報告があります。これは、脳の神経が再び活発に働き始めているサインと考えられます。
もちろん、すべての研究で同じような結果が出ているわけではありませんが、多くの専門家が「運動は脳の信号バランスを整える」と考えています。



運動って、ただ筋肉を鍛えるだけじゃなくて、”脳の元気”も取り戻してくれるんです。
③.神経のリズムを整えて動き出しを軽くする
パーキンソン病では、脳の中で動きをつくる信号のリズムが、必要以上にピタッと揃ってしまうことがあります。
これは、体を固める方向に働きやすく、動き始めが難しくなったり、途中で体が止まってしまう「すくみ足」の現象と関係していると考えられています。
研究では、ランニングマシンや自転車こぎの運動によって、この「揃いすぎたリズム」が和らぐことが分かっています。特に自転車こぎは、歩くのが不安な方でも取り入れやすい運動です。
また、運動は注意力や眠気にも良い影響を与える可能性があり、動きだけでなく日常生活全体の快適さにつながることが期待されます。



脳のリズムも運動することで整えられるんです。
④.脳の血流を高めて頭をスッキリさせる
パーキンソン病では、脳の一部で血流が減りやすく、考える力や計画を立てる力の低下と関係していると考えられています。
脳の奥深くにある運動に関わる「基底核」では、研究によって血流の変化に違いが見られるものの、細かい血管の流れが落ちると、炎症や代謝の乱れ、余分な鉄のたまりなど、悪循環が起こる可能性があると言われております。
運動をすると、使っている部分の脳は「もっと栄養と酸素が欲しい!」と信号を送り、その結果、血流が増えてくれます。また、運動の強さが上がるほど、この血流も増える傾向があります。さらに、運動は新しい血管をつくる手助けをする物質の働きを活発にし、細かい血管のネットワークを育てる可能性もあります。
こうして脳は、より多くの“新鮮な空気”と栄養を受け取れるようになります。
パーキンソン病において、この効果が直接的に証明されている研究はまだ少ないものの、有力なメカニズムの一つとして注目されています。
⑤.脳の“お掃除ルート”を流す
脳には体のようなリンパ管がありません。その代わりに、脳の中では脳脊髄液という透明な液体が血管のまわりを通って出入りし、いらなくなった物質を運び出しています。これが「グリンパ系」と呼ばれる“お掃除ルート”です。
パーキンソン病では、この仕組みがうまく働かなくなり、不要なたんぱく質(αシヌクレインなど)が脳にたまりやすくなる可能性があります。運動は、血流や脈の動きを高めることで、この掃除の流れを後押しします。また、よく眠ることで夜間の掃除が活発になるため、運動による睡眠の質向上も間接的な助けになります。
⑥.炎症の火をしずめて神経を守る
パーキンソン病では、脳の中で“炎症の火”が長くくすぶっていることがあります。これは免疫細胞が過敏に反応し、神経を守るどころか傷つける方向に働いてしまう状態です。
運動には、この炎症の火力を弱める働きがあります。体の中で「落ち着かせる信号」を増やし、バランスを整えてくれるのです。
特に、呼吸やストレッチ、軽い有酸素運動を組み合わせた活動は、全身のこわばりや張り詰めた感じを和らげ、気持ちや体の軽さにもつながります。



ヨガや太極拳は炎症を鎮める効果がありそうですね。
⑦.お腹から脳へ健康を届ける
パーキンソン病では、便秘やお腹の張りといった症状がよく見られます。最近の研究では、腸の中の細菌バランスが脳の健康にも影響することが分かってきました。
運動は、腸の動きを促し、腸内細菌の種類を豊かにします。その中には「酪酸」という物質を作る細菌もいて、この酪酸は脳の炎症を落ち着かせる方向に働くと考えられています。食後に軽く体を動かしたり、腹式呼吸を取り入れることも、この“お腹から脳へのサポート”になります。
⑧.細胞のサビを落としてエネルギーを守る
神経細胞は、小さな発電所のような「ミトコンドリア」でエネルギーを作っています。パーキンソン病では、この発電所が疲れてしまったり、活性酸素という“サビ”が増えて細胞を傷つけることがあります。
適度な運動は、細胞に軽い刺激を与えて「サビ落とし」の仕組みを鍛え直し、ミトコンドリアの量や質を改善します。その結果、神経細胞の“燃費”が良くなり、長く働ける状態を保つことにつながります。ただし、やりすぎは逆効果になるため、無理のない範囲で行うことが大切です。



無理のない範囲で継続することが大切です!
⑨.体が作る“元気の伝書鳩”を活かす
イリシンは、運動をすると筋肉や脳から作られる小さなたんぱく質のかけらです。血液にのって全身を巡り、脳にも届くと考えられています。
研究によれば、このイリシンは神経を守る物質の分泌を促し、炎症や酸化ストレスを和らげる働きを持つ可能性があります。まだ人での研究は始まったばかりですが、「運動で自分の体が作り出せる薬のようなもの」として注目されています。
どの運動がいい?強度・頻度・安全対策のリアル
今回の総説の結論としては、現時点の研究では“高めの強度の有酸素”が有望という流れです。ただし、病気の進行度合い・その他の合併症・体力レベルは人それぞれです。なによりも安全に継続できることが最重要です。
歩行が不安なら自転車こぎ、水中歩行、座位エクササイズ、ダンス、太極拳、VR活用など“転倒しにくい形”へアレンジしてみることが大切です。



繰り返しお伝えしていますが“最高の運動”よりも“自分自身が続けられる運動”が重要です。
運動はパーキンソン病ケアの“柱”
この総説は、動物モデルの知見に支えられている部分が少なくありません。
ヒトでの検証は増えてきましたが、強度・頻度・種目の最適解はまだ確立途中です。
つまり、「今ある根拠で“できること”を積み重ねながら、あなた自身の体で“何が効くか”を一緒に見つける」という段階です。効果を実感しながら、自分に合った運動を見つけて継続していくことが大切だと思います。
運動は、今回の総説を紹介したようにパーキンソン病の多面的な病態に同時多発的に働きかけてくれます。
どれか一つが劇的に効く、というより、小さなプラスの積み重ねが一つの大きな流れを作るのがリハビリです。
あなたに合う小さな一歩から始めていきましょう!
引用
- Wilson, A.C.; Pountney, D.L.; Khoo, T.K. Therapeutic Mechanisms of Exercise in Parkinson’s Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2025;26:4860. DOI: 10.3390/ijms26104860
- URL: https://doi.org/10.3390/ijms26104860


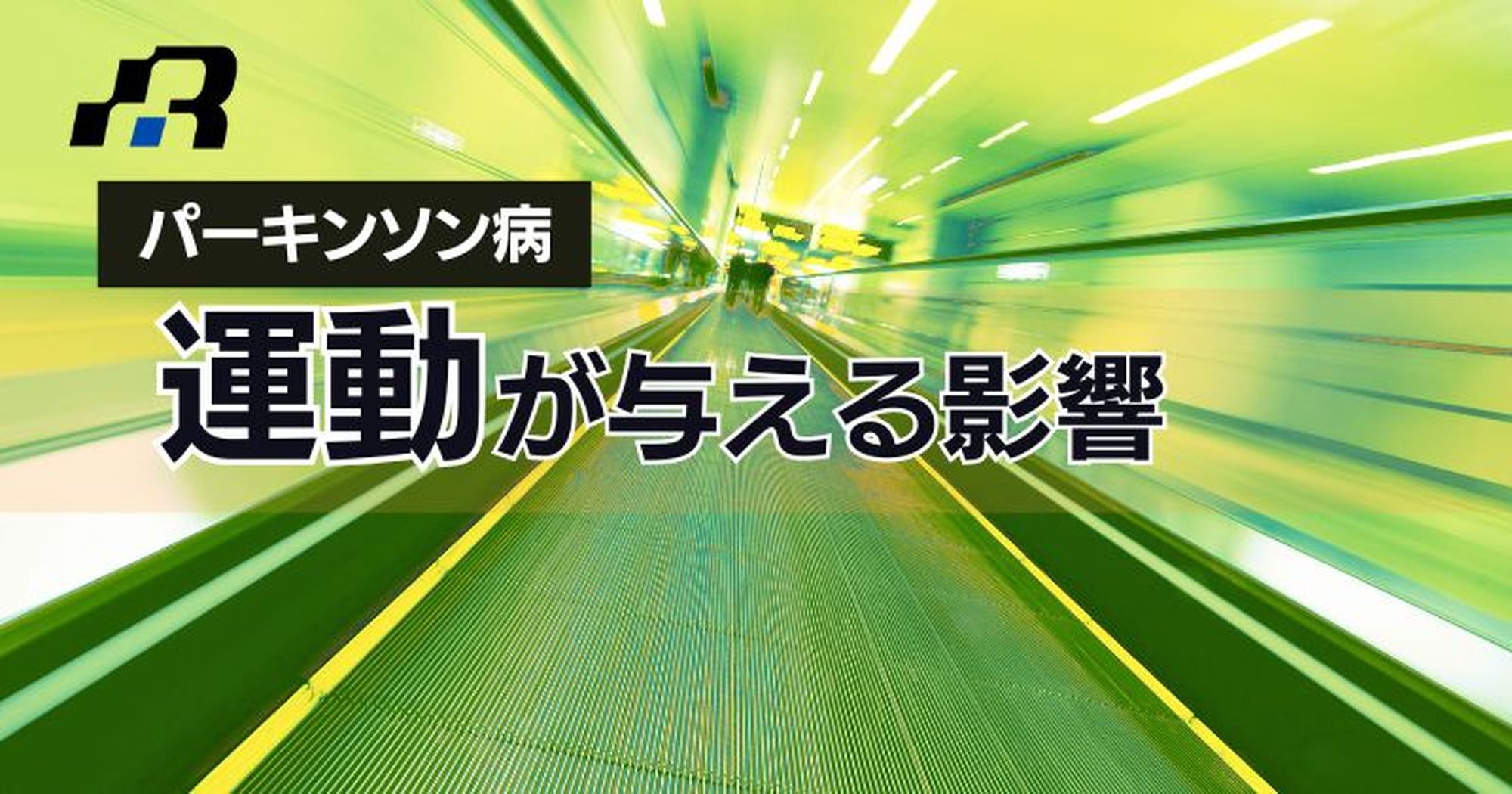
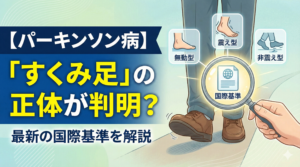

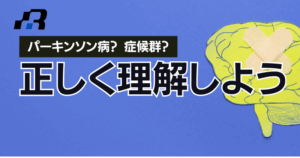




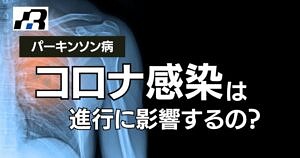
コメント