
今回のテーマは、パーキンソン病の新しいリハビリの形として注目されている「遠隔リハビリ(オンラインリハビリ)」についてです。
「コロナ禍で病院に通えなくなった」
「家でできる運動はないの?」
「自費リハビリで何ができるの?」
こうした悩みを持つ方が増えている今、遠隔リハビリがどれだけ有効なのか、信頼できる研究データをもとにお伝えします。
遠隔リハビリってどんなもの?
まず、「遠隔リハビリって何?」という方もいらっしゃるかもしれません。
遠隔リハビリとは、スマホやパソコンを使って、インターネット経由で理学療法士とつながりながら自宅でリハビリを行う方法です。
この研究では、パーキンソン病患者56名が参加し、週2回、Zoomを使って椅子に座ってできる運動や発声練習、認知トレーニングなどを6ヶ月間実施しました。
 白石
白石「イスに座ってできる内容なら、“体力が落ちてて不安”という方にもハードルが低いですよね。しかも医師や理学療法士のサポートつき!」
遠隔リハビリの結果は?―使いやすくて、気分も前向きに
さて、本題です。6ヶ月間の遠隔リハビリの結果はどうだったのでしょうか?
まず、参加者の91.1%が「満足した」と回答しています。
また、91.9%の方が「運動の習慣がついた」と答えています。これはとても大きな意味を持ちます。
たとえば、50%の方は「手足の動きがよくなった」と感じており、さらに71.4%の方が「気分が前向きになった」と回答しました。



「運動で気分が明るくなるのは、脳にも良い影響を与えるんですよ。
とくにパーキンソン病では“やる気の低下”が起きやすいので、気持ちの変化はとても大事です」
一方で、パーキンソン病の生活の質(QOL)を測る「PDQ-39」という検査では、全体としてはわずかに悪化している傾向がありました。
でもその中でも、19名(約3分の1)の方は生活の質が改善していました。
改善した人たちには、歩行や日常生活動作(ADL)、感情の安定、社会的なつながりの面で良い変化が見られたそうです。
自費リハビリとの関係は?
最近は、病院の保険リハビリが終わってしまったあとも、「もっと続けたい」と希望される方が増えています。
そのときに使えるのが、「自費リハビリ」という選択肢です。
遠隔リハビリも、その一種と言えます。
自費リハビリは、保険制度の制限に縛られず、自分のペースで必要な支援を受けられることが特徴です。
特にパーキンソン病のように継続的な理学療法が大切な病気では、自費であっても“続けられる環境”を整えることがとても大切です。



「『もうリハビリは終わりです』って言われても、パーキンソン病の症状は止まってくれませんよね。自分で“続ける仕組み”を持つことが大事なんです」
パーキンソン病の方にとって大事な“仲間とのつながり”
もうひとつ、この研究で印象的だったのは、「他のパーキンソン病の患者さんと一緒にリハビリができたことが良かった」という声が多かったことです。
73.2%の方が、「同じ病気の仲間と一緒にできてよかった」と答えています。
コロナ禍以降で外出が減り、人と話す機会も少なくなっていた中、同じ病気を持つ仲間と画面越しでもつながることは、大きな心の支えになったようです。



「私たち理学療法士が支えるのも大事ですが、やっぱり“同じ立場の仲間”の存在って大きいですよね。そこに遠隔リハビリの新しい可能性を感じました」
どんな人に向いているの?
この研究では、
「移動が大変」
「病院が遠い」
「家から出にくい」
という方にも、遠隔リハビリは大きな可能性があると述べられています。
実際に参加された方の平均年齢は73.8歳。
「高齢だからオンラインは無理」と思われがちですが、家族のサポートやスタッフのフォローがあれば、十分に使えることも証明されました。
リハトレスタジオ世田谷で運営しているオンラインサロン「プロエル」に参加されている平均年齢と同様の結果でした。
おわりに:理学療法×遠隔×自費リハビリの可能性
今回の研究を通して見えてきたのは、遠隔リハビリは「単なる代替手段」ではなく、新しい形の理学療法の一つになりうるということです。
もちろん、すべての人にとってベストな方法とは限りません。
でも、
「通院が難しい」
「仲間とつながりながら続けたい」
「自分のペースで運動を習慣にしたい」
そんな方にとっては、とても魅力的な選択肢です。
自費リハビリのひとつとして、遠隔リハビリを取り入れることで、もっと自由に、もっと自分らしくリハビリを続けられる時代が、もう始まっているのかもしれません。
参考文献
Okusa S, et al.“Satisfaction, Effectiveness, and Usability of Telerehabilitation for Parkinson’s Disease Patients”.Published in Journal of Rehabilitation Medicine, 2025
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013856.pub2/full


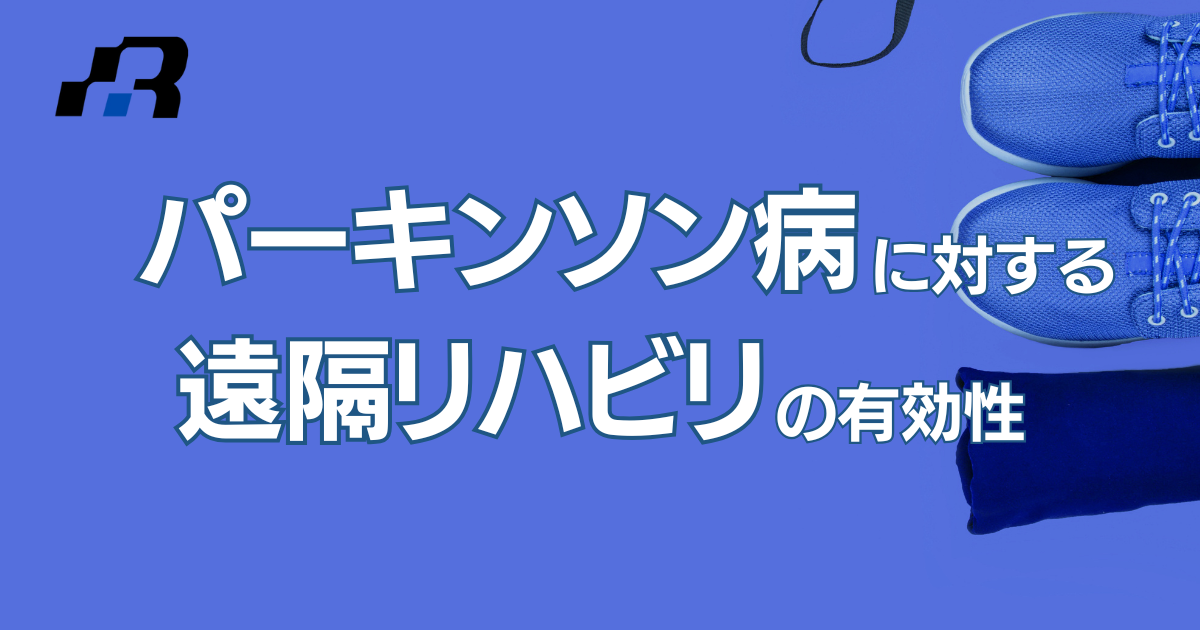
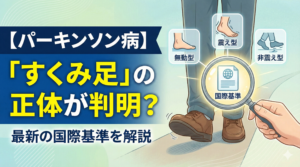

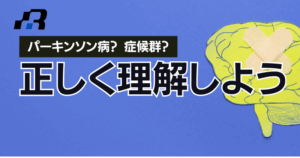





コメント