こんにちは。リハトレスタジオ世田谷の白石哲也です。
今日はひとつ、個人的にとても嬉しいご報告があります。
このたび私は、国立がん研究センターが提供する「ICR臨床研究入門」にて、
• 「臨床研究の基礎知識講座」
• 「臨床研究・治験従事者研修2021」
この2つの研修を修了し、修了証を取得することができました。
臨床の現場に身を置いてもう十数年。
これまでずっと「目の前の患者さん」に寄り添いながら、試行錯誤を繰り返してきました。
でも最近は、ふとこう思うことが増えたんです。
「自分の臨床って、本当に“科学的”と言えるんだろうか?」
「ひとりの成功体験を、どうやって“再現性のある知見”として社会に還元できるんだろう?」
研究って、特別な人だけのもの?
私は正直、「研究」という言葉に長いこと苦手意識がありました。
専門用語ばかりで、堅苦しくて、一部の大学関係者や、論文を読み慣れた人たちのものだとどこかで思い込んでいました。
でも、パーキンソン病や神経難病の方たちと向き合う中で、どうしても伝えきれない「違和感」や「ジレンマ」が出てきたんです。
たとえば――
• 訪問リハではリハビリの質に格差がある
• 誰を選ぶかで、病状の経過が変わってしまう
• 本人やご家族が、どこに相談すればいいか分からずにいる
そういった“現場のリアル”を、もっと言語化したい。
そして、患者さんの声をエビデンスに変えて、世の中に届けたい。
そう思ったのが、今回の研修を受講しようと決めたきっかけでした。
研修の内容は、まさに「知のスタートライン」
今回の研修プログラムでは、
• 臨床研究と治験の違い
• 倫理指針の理解と遵守
• オプトアウトとインフォームドコンセントの本質
• 個人情報保護のルールと感度 など
学びながら何度も立ち止まって、
「これ、ちゃんと分かっていなかったな…」と思う場面ばかりでした。
特に心に残ったのは、“人を対象とする研究”がどれほど慎重であるべきかという点です。
リスクが少ないと思っても、どこまでが「介入」になるのか。
どんな情報が「個人情報」に当たるのか。
そして、どんなときに「文書による同意」が必要になるのか。
普段、何気なく使っている医療用語や手続きも、研究というフィルターを通してみると、まったく違う景色に見えてくる。
そんな気づきにあふれた学びの時間でした。
これから、私がやりたいこと
今回の研修を通じて、私は「質的研究」にチャレンジしてみたいと考えるようになりました。
たとえば――
• パーキンソン病患者さんが感じている“訪問リハビリの選択の不自由さ”
• 自費リハビリを選ぶ人たちの「本音」
• リハビリを受けられない地域格差や心理的ハードル
そういった、数値では測れない「生の声」を、丁寧に拾い上げていきたい。
そして、「AIリハ支援」や「専門職選択型の仕組み」を社会に提案していく――
そんな未来を思い描いています。
最後に
私は理学療法士です。でも、同時に「ひとりの市民」でもあり、「当事者の味方」でありたいと思っています。
研究は、私たちの日常から遠い世界の話ではありません。
現場にある違和感や気づきを、社会の課題として発信していくための武器にもなります。
今回の学びを、これからの実践と活動にしっかり活かしていきます。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。
そして、もし同じように「臨床×研究」に興味がある方がいたら、ぜひ気軽に声をかけてくださいね。
臨床の現場から、未来の医療を動かす一歩をしていきたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。


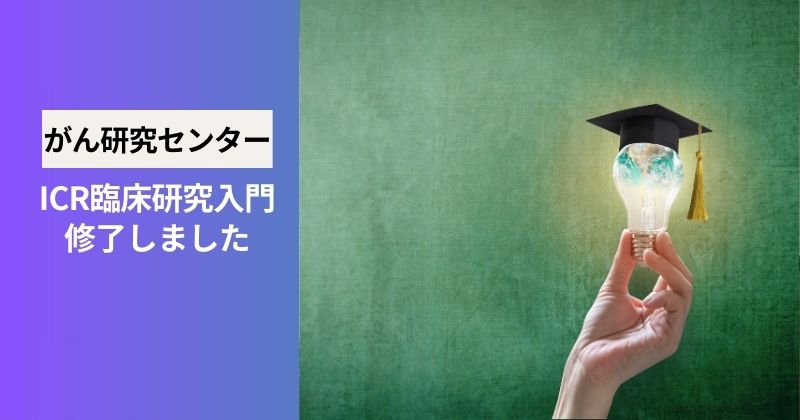




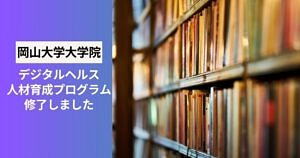

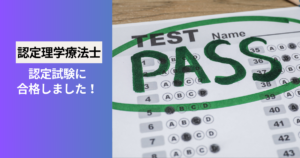

コメント